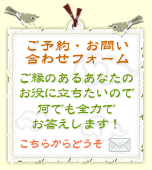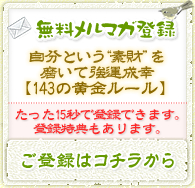猫の妙術
勝軒という剣術者がいた。勝軒の家に大きな鼠が1匹いて、白昼堂々と部屋中走り回るので、
勝軒はその部屋を閉め切って、飼い猫に鼠を捕らえさせようとした。しかし、その鼠は飼い猫
の面に飛びかかり、あるいは喰いつくなどしたので、飼い猫は泣き声を上げて逃げてしまった。
仕方なく勝軒は、近辺から抜群に強そうな猫を集めて来て、少し隙間を開けて部屋に追い
入れたものの、くだんの鼠は床の隅にいて、猫が来れば飛びかかり、喰いつき、あまりに
も凄まじいものだから、猫どもは全て尻込みしてしまい、どれ1匹として鼠を捕ろうとしない。
この様子を見ていた勝軒は腹を立て、自ら木刀を持って鼠を追い、打ち殺そうとするが、
木刀はまるで鼠に当たらぬばかりか、戸障子や襖を叩き破ってしまう始末。勝軒は
大汗を流しながら、下僕を呼ぶと大声で言った。
「六、七町先に、並々ならぬ古猫がおると聞いている。すぐに借りて来なさい」
早速、借りて来た猫を見れば、あまり利口そうでもない。が、かの部屋に入れると、
例の鼠は身をすくめてしまって動かない。古猫は何事もなげに、ノロノロと鼠のそば
へ歩み寄ると、難なく鼠をくわえて戻って来た。その夜の事である。
勝軒の家に多くの猫どもが集まり、かの古猫を上座に講じ、いずれの猫どもも、その前
にひざまずくと古猫に言った。
「我々は抜群の猫を称賛され、その道の修行を積み、鼠ばかりかイタチ、カワウソの類
まで捕らえられるほど、爪も磨いて研鑽してきた。しかしながら、未だに今日のような
強い鼠に出会った事はなかった。それを御貴殿は、何の術を持ってか簡単に捕らえ
られたが、願わくば、我らにもその妙術を教えて頂きたい」
すると、古猫は静かに笑って言った。
「若い猫の皆さん。皆さんは一生懸命に働かれたではありませんか。ただ、思わぬ不覚
を取られたのは、未だ正しい道理にかなった技法をご存知でないからでありましょう。
まずは、皆さんの修行のほどから、お聞きする事にしましょう」
古猫の言葉に、鋭い顔つきの黒猫が1匹、前に進み出て言うには、私は鼠を捕獲する家
柄に生まれ、以来、その道に心がけてきた。七尺(約2メートル)の屏風を飛び越え、小さ
な穴にもぐり、小猫の時から早業、軽業を得意とし、時には眠ったふりをして策略をめぐ
らし、不意に桁や梁を走る鼠といえども、一度として捕り損じた事はなかった。ところが
今日、思いの外の強鼠に出会って、一生の不覚を取り、はなはだ心外に思っている、と。
聞いて、古猫は口を開いた。
「あぁ、あなたの修行は技法第一主義というもの。従って狙う心が先に立っているのです。
昔の人が技法を教えたのは、その道筋を教えんがためで、故に、その技法は容易では
なかった。その中に深い真理があるのだが、今日では技法だけを専らにし、ために種々
の技を創り、技巧を極めるので、単なる技比べになってしまった。それでは、技巧が
尽きれば、どうにもなりますまい。小人が技巧に走り、才覚に溺れると、全てそのよう
になろう。心の働きといえども、道理に基づかず、巧を専らとする時は、かえって害の
多いもの。これを反省して、よくよく工夫する事でしょう」
次に、虎毛の大猫が1匹まかり出ると言った。
「私の思うに、武術は“気の持ち方”を貴びます。ゆえに、気を練る事に長い修行を続け
てきた。そのため、今はその気力も固く強く、天地に充ちている。気合でもって敵を倒し、
まず勝利して後すすみ、声に従い、響きに応じて、鼠を左右につけ、変化にも応じる事
ができる。行動するにも意識せずして、自然に湧き出る如く振る舞う事ができ、桁や梁
を走るも可能だ。ところが、彼の強鼠は来るに形なく、往くに跡がない。これはどう
いう事なのでありましょうか」
古猫が言うには、その修練は、気の勢いによって働くものでしかない。つまり、自らの
気力を頼みとするもので、最前の者ではない。我れ破らんと欲すれば、敵もまた破ろう
としてくる。また破ろうとして破れぬもののあった時はどうするか。
決して己だけが強く、敵はみな弱いというものではない。天地に充が如き気と思っている
ものは、全てうわべだけの勢いでしかない。それは孟子の浩然の気と似て、実は全く相
違するものなのだ。孟子はよく見える目を持ち、物事を見分ける知力を備えて剛健だが、
あなたのは勢いに乗じた剛健であるから、その効果のほどもまた同じではないのだ。
例えば、滔々と日夜流れる大河と、一夜の洪水の勢いとの違いというもの。気勢に屈し
ない敵がある時はどうするのか。俗に“窮鼠猫を噛む”の例えもある。そのような敵は、
必死になり、生命を忘れ、欲を忘れ、勝負を度外視し、身の安全など心中になく無心
である。こうした敵に、勢いだけでどうして勝てようか。
古猫の話が終わると、灰色の少し年を経た猫が、静かに前へ進み出て質問した。
「仰せの通り、気は旺盛ではあっても象(かたち)があり、象のあるものは微小であっ
ても見えるもの。私は長く心を鍛練して、気勢をなさず、相争う事なく、何事も相和
してきた。私の術は幕を張り巡らせて、つぶて(石)を受けるようなもので、強鼠と
いえども、私に敵しようとしても相手ではない。ところが今日の鼠は、勢いにも屈
せず、和にも応じず、まさに神の如くで、私は未だにこのような鼠を見た事がない」
灰色の老猫の話に、古猫は答えて言った。
「そなたの和は自然の和ではなく、考えて成せる和であり、従って気を外さんとしても、
わずかな妄念が生じれば、敵はそれを知るのである。また、私心をはさんで和を成せば、
気は濁って惰してしまうものだ。思い考えて成せば、何事も自然の感を塞いでしまうため、
妙手はどこからも生じない。ただ、思わず、成す事もなく、感に従って動けば生ぜず、
天下に敵すべき者はいなくなる。
とはいえ、各々が修行するところのものを、全てが無用の事というのではない。気の
あるところ必ず理があり、理のあるところ必ず気は離れずにあるから、動作の中に理
に至るものはあり、気はまた一身の用を成すものである。
その気が大らかなる時は、物に応ずること無窮(むきゅう)で、和する場合は、力を
持たずして金石に当たろうとも、決して折る事もない。わずかに思考する事が、全て
作意となってしまうのだ。ゆえに敵する者は心服しない。
何の術をも用いる必要はない。ただ無心に、自然に応じられるが良かろう。道には
極まるところはないから、私の言うところをもって至極と思ってはならない。
昔、私の郷に猫がいた。終日眠っていて気勢もなく、木で作った猫のようであった。
人々も、その猫が鼠を獲るのを見た事がなかったが、その猫の行く所、近辺に鼠の
姿を見る事はなかった。そこで、私はその猫の所へ行き、その理由を質したので
ある。が、その猫は答えず、4度も問うたが、4度とも答えなかった。これは答え
なかったのではなく、答える理由がなかったのであった。
それでわかった事だが、真に知るものは言わず、言うものは真を知らないものだ。
その猫は己を忘れ、ものを忘れて無物に帰していたのである。まさしく“神武に
して不殺(※註)”というものであった。私もまた、彼に遠く及ばなかった」
古猫のこの話を、勝軒は夢の如く聞き入っていたが、やがて、古猫に会釈すると
やおら口を開いていった。
「私は剣術の修行を始めて久しいが、未だその道を極める事ができないでいる。
今宵は各々のお話を聞いて、ずいぶん悟るところがあった。願わくば、なお
その奥義を示して頂きたいのだが・・・」
古猫曰く、
「否。私は獣であり、鼠は私の食するところのもの。私がどうして人のする事を
存じましょうや。しかしながら、私が密かに聞いた事がある。“それ剣術は、
専ら人に勝つためにあらず。変に臨みて、生死を明らかにする術なり”と。
武士たる者は常に心を養い、その術を修行しなければなりません。故に、
まずは生死の理に徹し、不疑不惑、才覚・思慮を用いずに、心気和平にして、
静かに安らかで平常心であれば、変化に応じる事は自由自在となる。
だが、この心にあらざる場合は、状(かたち)が生じ、敵が生まれ、相対して
争う事にもなって、変化に適応できなくなるのだ。つまり、己の心が先に死地
に落ちて霊明さを失うので、どうして快く勝負が決せられよう。例え勝つ事が
あっても、それは“まぐれ勝ち”でしかなく、剣術の本旨ではない。
無心無物といっても、空しいといったようなものではない。心はもともと形も
なければ、従って物を蓄える事もできない。そこのわずかでも蓄えるものが
あれば、気もまたそこへ拠ろうとし、そうなれば豁達(かったつ)自在に在る
事は難しくなる。向かうところは過となり、そうでないところは及ばなくなり、
過は勢い溢れて留まらず、及ざる時は用を成さなくなり、共に変化に適応
できなくなるのだ。
私が言うところの無心、無物とは、蓄えず拠らず、敵もなければ我もなく、易に
いうと、この“思う事なく、成す事なく、ひっそりと動かず、天下の事に感じて
ついに通ず”で、この理を極めるに近い」
そこで勝軒は、再び質問した。「敵なく、我なくとは・・・」古猫は言う。
「我あるが故に敵があるのだ。我がなければ敵もあるまい。敵というのは、陰・陽・
水・火と同様である。およそ形あるものは、必ず対するものだ。己の心に象(かたち)
がなければ、当然、対するものもない訳で、争う事もない。これを“敵もなく、
我もなし”という。物と我ともに忘れて、静かに安らかに、一切の妄念を絶てば、
和して1つになろう。
敵の形を破っていても、我もそれを知らない。否、知らないのではなく、そこに
心がなく、感のままに動いている、という事であろう。この心は“世界は我が世界”
であって、是非、好悪などにとらわれない事を指す。
全ては己の心から苦楽・得失が生じるのであり、天地広しといえども、また、己の
心の外に求めるものはないのである。
古人曰く、“眼裏塵(ちり)有りて三界窄(すぼ)く、心頭無事一生寛(ゆたか)なり”と。
すなわち、目の中にわずかの塵が入れば、眼を開く事ができない。外来、あるべきは
ずのないところに、ものが入るからそうなる訳だが、これは先の心の例えなのである。
また、古人の曰く、“千千万万人の敵の中に在って、この形は微塵になるとも、この
心は我が心なり”と。
孔子曰く。“匹夫も志を奪うべからず”と。もし、迷う時は、その心が敵を助けるのだ。
私の言う事は、ここまでである。
後はただ、自ら省みて己に求める事だ。師はその事(わざ)を伝え、その理を悟すだけだ。
その真を得るのは、我にある。これを自得という。あるいは、“以心伝心”ともいう。
禅学だけではなく、聖人の心法から芸術の末に至るまで、自得のところは全て以心伝心
である。教えるというのは、己にあっても自ら見る事のできぬところを、指して知らしめる
だけである。師から授かるのではない。
教えるのも易く、それを聞くのも易い。但し、己にあるものを確実に見つけ、己のもの
とするのは難しい。これを修行上の一眼目という。悟りとは、妄想の夢の覚めたもので、
覚(さとる)という事とも同じであり、格別変わった事ではないのである。
(※註)周の文王を賛えた言葉。文王は神の如き武勇を備えながら、あえて兵を興さず、
人を殺さずに、泰然として時を待ったという。
/1992年剣道日本4・5号「秘伝書抄訳シリーズ(佚齋樗山子著:中井一水訳)」より