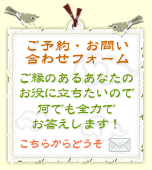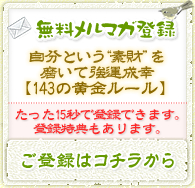肩書き
社会人になれば、名刺の一つも作ろうと思う。多くの名刺には、組織の名称、自分の名前、
それから肩書きがついているものも多い。名刺交換をする時には、「何某という組織の何某
という役職の・・・」と自己紹介したりする。立派な肩書きを見れば、それなりの人だと信じて、
丁重に対応して見せたりもする。決して、その対応が間違いであるとは思わない。以前、上司
であった人と偶然取引先で会った。上司は転職をしていて、一介の営業マンになっていた。
前の会社のやり方とは、どうしても価値観が合わず、今の仕事に就いたと言う。実力社会に
飛び込んだのだ。勇気ある元上司の決断をうれしく思った。しかし、彼の言葉や態度には、
過去の堂々たる勢いがなくなっていた。一介のセールスマンになったと、何度も言葉を繰り
返して、お辞儀をして見せた。お辞儀をしているのか、うつむいているのか、わからないくらい。
彼の輪郭が薄らいでいった。以前の会社と価値観が合わないことは、はっきりしていたが、
彼の価値観がどこにあるか見えていないのだと感じた。肩書きというのは、人生のある時期
の位置付けについて、便宜上、その時の社会が個人を名づけるものである。その人の個性
を決定づけるものではない。人生を列車の旅に例えるなら、肩書きは今通過する駅の名前
のようなものであって、大切なのは、どんな意味のある旅を、どんな列車でしているのかと
いう事である。その時、偶然もらった肩書きも一つの名前であるなら、自分のキャリアに、
自由につける自分の形容詞も、立派な肩書きという名前になる。王や長嶋が「ひまわり」なら、
私は一輪の「月見草」であると語ったスポーツマンがいた。「生涯一捕手」と語った人である。
絶賛の肩書きである。未だかつて、この肩書きを人に使われたことは、一度もない。
捕手の目で、社会を見続け、行動し続けるのが、この人が、自らに課した使命である。
そして、その肩書きは、彼のブランド名である。最期まで、その人らしく生きてもらいたいと
願わずにいられない。新入社員のキャリア研修を行った時に、自分のことを「白い色鉛筆」
と形容した女性がいた。22歳。「私は見ての通りの新入社員。見た目も細いが、中身も細い。
仕事をしても、ほとんど色はうつらないが、なくてはならない色。確かに私は、そこに存在
しています」そう語った。拍手を送った。「できれば、名刺を使わない自己紹介ができる
人間になりたい」とも言った。名刺を欲しがらない社会人がいることを、初めて知った。
彼女は、情報関係のソリューション営業を担当している。「私は情報ツールがきちんとし、
能力が発揮できる環境をつくる仕事をしています。それは、私達の会社が作った機器が
怠慢な仕事をしていると、悲しくなるからです。会社は、私のそんな遣り甲斐を助けてくれる
スポンサーです。でしゃばったことは決してしません。一度、貴社の情報ツールの働き具合
を見せて頂けませんか?」名刺は、自己紹介が終わってから差し出す。あれから何年も
経っているが、でしゃばらずに、どんな色にもなじんで、自分を発揮する姿は「白い色鉛筆」
そのものである。
/山本 正樹(経営コンサルタント・株式会社 理想経営代表)
♪今日のラララ~ン♪ ワンタン鍋を作ったつもりが、中身が多すぎて小龍包鍋になっても~た(笑)